
こんなお悩みにお応えします。
実はわたくし、先日、会社で初めての昇格試験を受けました。
試験内容は面接と小論文だったのですが、
”面接なんて就活ぶりで、ちゃんと質問に答えられるか不安・・・”
”そうあるチャンスじゃないから落ちたくない。とにかく不安・・・”
と、日頃の業務に身が入らず、モンモンとした日々を過ごしていました。
こう思いながら、上司に相談し、自分でググりながら対策を続け、先日無事に試験が終わりました。
まだ合否は出ていませんが、具体的な対策方法やポイントについて、記憶が新しいうちに紹介していきます。
スポンサードサーチ
【昇格試験】試験対策のポイントを3つ紹介【対策して不安と緊張を乗り切ろう】

試験対策は、以下のポイントを意識して行うのがよかったです。
・昇格基準を読み込み、キーワードをピックアップする
・キーワードに沿う自分の過去の取り組みをピックアップする
・キーワードを入れた資料を作成する
面接資料も小論文も、いきなり資料を作り出すのではなく、まずは資格基準を確認しましょう。
ポイント
資格基準を読み、どのような人物が求められているのかを確認する
昇格試験の合否基準
なぜ、まず基準を確認すべきかというと、昇格試験というのは、昇格するための基準を超えている人物か否かを判断する試験だからです。
つまり、仕事の成果ではなく、あなたの過去の取り組みが基準を超えたものになっているかどうかで判断されます。
ここを意識をしないと、どうしても業務報告会的な内容になりがちです。

どこの部署でも、肩書きは共通
例えば、製造業の会社ひとつとっても、商品企画、研究開発、生産管理、品質保証、営業、サービス、人事、総務、財務など、多種多様な業種が存在します。
しかし、どこの部門でも同じ会社であれば、部長、課長、チームリーダーなど肩書きは同じですよね。
つまり昇格試験では、人物としてある一定の基準を満たしてるか否かが問われます。
もちろん、求められる資格基準は、上になればなるほど抽象度が上がって難しくなります。
なので試験では、
・自分なりに考え、行動できているか
・周囲に働きかけながら仕事ができているか
・自ら課題を発見し、解決できているか
とか、こういったことが評価されます。

部長曰く、仕事の成果や内容自体は重要視されないようです。
なので、まずは自分が受ける資格の基準を確認して、それに合うキーワードを入れた資料で発表や面接を受けることが必要です。
ポイント
資格基準に沿ったキーワードを資料に散りばめる
【昇格試験】面接対策のポイント

面接試験のお題は、
「去年と今年の重要テーマについて、取り組みとその成果を5分で説明せよ」
というものでした。
この面接への対策で意識したポイントを紹介します。
それは、繰り返しになりますが、
・自分が取った行動、プロセスを説明すること
・課題に対しての問題点と自分が取った解決策を説明すること
です。

業務報告会にならないように!
自分の考えと行動にフォーカスする理由は、資格基準に沿った内容にできることと、単純な業務内容報告会にならないようにするためです。
とはいえ、実際問題「上司からの指示にしたがっただけで、自分で考えて行動して、成果を出せたことなんてないっす・・・」という人が、ほとんどだと思います。

こういう場合は、「上司と相談しながら、このように考え、このように進めました」という説明にしてOKです。
自分で考えて行動した例を思い出せないという人は、自分が担当したプロジェクトを進める上でのプロセスを振り返り、その時の進め方を説明しましょう。
ポイント
過去の仕事のプロセスを振り返り、そのときの行動と結果を説明する
具体例
僕は、テーマの目的、背景、目標を説明した後に、取り組みについては、以下のように発表をしました。
参考
”チームリーダーに商品の改善アイデアを打ち上げたこときっかけに、メンバーでアイデアを出し合う会議を開催しました。結果、改善アイデアを*件抽出できたので、それらアイデアの費用対効果を明確化しました。そして、コスト成立できたアイデアを実際に商品に導入できました。現在は、新商品への横展開もできています”
この事例で、自分で考えて行動できたことなんて、アイデアの打ち上げくらいです笑。
それ以降は、リーダーの指示の下で会議を開催し、進行していきましたが、実際に自分が意見をとりまとめながら進めたことは事実です。
指示の下でも、自分が取った行動やプロセスは必ずあるはずなので、自分がとりまとめた仕事や関わった仕事を振り返ってみましょう!
ポイント
過去に取り組んだ仕事の中で、自分のとった行動や仕事のプロセスを振り返る
スポンサードサーチ
【昇格試験】小論文対策のポイント
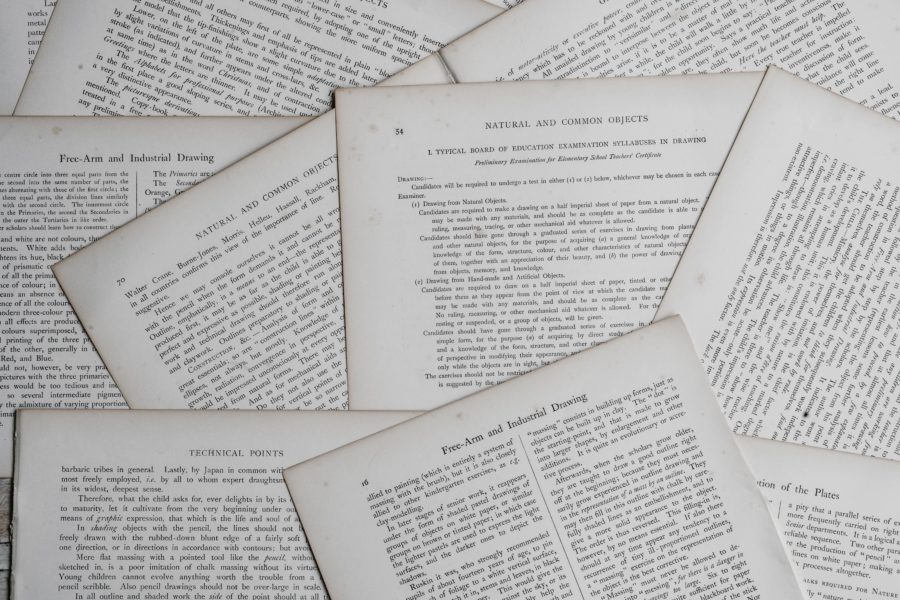
続いて、小論文対策です。
お題は
「昇格後にあなたに求められる役割とそれに対する具体的な行動について述べなさい」
でした。
これに対して、注意したポイントは
・「結論→理由→反論理解→具体例→結論」という流れにすること
・お題に合っていない「現代の背景」を書かないこと
です。
解説してきます。
小論文の書き方を理解する
小論文の書き方について、記事や動画を色々とみてみましたが、要するに、PREP法で書くのが最強とのことでした。
PREP法とは
P:Point(結論)
R:Reason(理由)
E:Example(具体例)
P:Point(結論)
これを、小論文の骨格となる
・序論(結論と理由)
・本論(反論理解と自分の具体的な行動例)
・結論(結論)
に、当てはめるだけでOKです。
文字量のバランスは、「序論:2、本論:6、結論:2」といったところでしょうか。
まぁ、とにかく、PREPです。

ポイント
小論文はPREP法で書くのが最強
「現代の背景」は不要
声を大にして言いたいのが、序論での現代背景は不要です。
小論文の書き方を調べていると、まず導入部分は「近年、〜の重要性はますます高まっている」という入りが多かったんですよ。
でもこれ、シンプルになんのために書くんですかね。理由が不明でした。
余分なことは書かず、まずお題に対しての結論を冒頭に書きましょう。

シンプルにPREP法で書けば、何も問題ありませんよ( ^ω^ )
振り返り
では、本記事の内容を簡単に振り返ります。
✔︎昇格試験対策をする上でのポイントは
ポイント
① 昇格基準を読み込み、キーワードをピックアップする
② キーワードに沿う自分の過去の取り組みをピックアップする
③ キーワードを入れた資料を作成する
✔︎面接試験対策でのポイントは
ポイント
・自分が考えて行動したことを説明する
・思い浮かばない場合は、過去に取り組んだ仕事のプロセスに注目する
✔︎小論文のポイントは
ポイント
・とにかくPREP法で書く
・現代の背景は不要
今回もありがとうございました!
