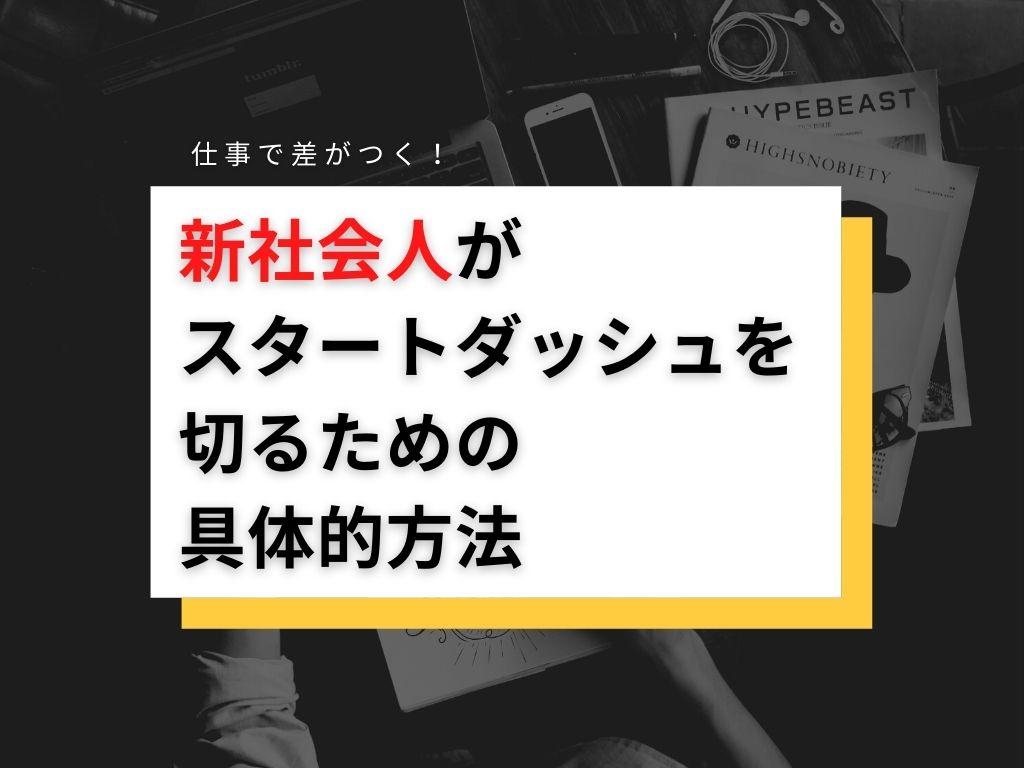晴れて新社会人となり、配属も終わっていよいよ仕事が始まりました。スタートダッシュを切ってどんどん成長したいのですが、仕事にはどんな感じで取り組んでいったら効果的ですか?
仕事で突き抜けた新社会人になる方法
結論、以下だと考えています。 順に説明していきます。必ず質問か要約をする
 仕事の説明やインプットをしてもらった際は、必ず質問か内容の要約をしましょう。
理由は、自分と相手の理解を深め、全体のレベルアップに貢献できるからです。
以前、新人に商品の構造説明をしたときに「〜ってなんですか?」「〜と〜で、なんで制御が分かれてるんですか?」「そもそもこの機能ってなんで必要なんですか?」と質問されまくったのですが、わかっていてもうまく説明できなかったり、理由までは知らなかったりと、不明点がたくさん出てきました。この疑問を解決するために、自分で調べたり、ベテラン社員に聞いたりしたので、まず商品理解が深まりました。また、質問に答えと理由でわかりやすく答えるために、僕の頭は常にフル回転状態でした。
そもそも、みんなの前で手を上げて質問するということ自体は、入社して数年経っていてもできない人はたくさんいます。それくらい怖いことなので、みんなの前で質問できるということ自体が、主体性や発言力を高めることに繋がります。
なので、新人が質問をすることは、知識や主体性、発言力が身に付くだけでなく、講師のレベルもアップさせるので、部全体の利益につながります。新人ができる、簡単で重要なアウトプットと言えますね。
質問が思い浮かばなければ、「要するにそれって〜っていうことですか?」という要約だけでも全然OKです。個人的には、下手な質問するよりよっぽどこっちのほうがいいと思います。
なぜかというと、自分だけでなく全体の理解度が高まるからです。
その要約が合っていれば、追加のコメントや補足をしてもらえますし、間違っていれば修正してもらうことができます。また、他のわかっていない人や聞き逃した人にとっては、再確認にもなります。
ということで、新人は必ず、質問や要約をしましょう。ただ、やりすぎると煙たがれることもあるので、場の空気を読みながらやってください笑。
仕事の説明やインプットをしてもらった際は、必ず質問か内容の要約をしましょう。
理由は、自分と相手の理解を深め、全体のレベルアップに貢献できるからです。
以前、新人に商品の構造説明をしたときに「〜ってなんですか?」「〜と〜で、なんで制御が分かれてるんですか?」「そもそもこの機能ってなんで必要なんですか?」と質問されまくったのですが、わかっていてもうまく説明できなかったり、理由までは知らなかったりと、不明点がたくさん出てきました。この疑問を解決するために、自分で調べたり、ベテラン社員に聞いたりしたので、まず商品理解が深まりました。また、質問に答えと理由でわかりやすく答えるために、僕の頭は常にフル回転状態でした。
そもそも、みんなの前で手を上げて質問するということ自体は、入社して数年経っていてもできない人はたくさんいます。それくらい怖いことなので、みんなの前で質問できるということ自体が、主体性や発言力を高めることに繋がります。
なので、新人が質問をすることは、知識や主体性、発言力が身に付くだけでなく、講師のレベルもアップさせるので、部全体の利益につながります。新人ができる、簡単で重要なアウトプットと言えますね。
質問が思い浮かばなければ、「要するにそれって〜っていうことですか?」という要約だけでも全然OKです。個人的には、下手な質問するよりよっぽどこっちのほうがいいと思います。
なぜかというと、自分だけでなく全体の理解度が高まるからです。
その要約が合っていれば、追加のコメントや補足をしてもらえますし、間違っていれば修正してもらうことができます。また、他のわかっていない人や聞き逃した人にとっては、再確認にもなります。
ということで、新人は必ず、質問や要約をしましょう。ただ、やりすぎると煙たがれることもあるので、場の空気を読みながらやってください笑。
すぐに手を付け、進捗を自分から報告する
 仕事を引き受けたら、最速で手をつけましょう。そして、進捗を自分から報告しましょう。
こうすることで、上司の負荷を減らすことができ、信頼されることができます。
僕がOJTリーダーをやったときにつくづく感じたのですが、任せた仕事をやっている素振りが見えなかったり、進捗連絡がなかったりすると、めちゃくちゃ不安になります。こうなると、自分の業務をやりながら、人の進捗を常に気にかけなければいけなくなります。これ、普通にパフォーマンスが下がるんです。正直「自分がやった方が早いから戻してもらおうかな」とさえ思っちゃいます。こう思われてしまうと、今後仕事を任せてもらえなくなる原因にもなりますし、信頼も得られません。
仕事の質を高めるには経験が必要ですが、スピードを高めることは誰にでもできるので、まずは速攻で手をつけ、1週間に1度は連絡・報告をしましょう。
ちなみに、よく「仕事は効果が高いものを選べ」とか言われますが、新人のうちからこれしてたら重要な仕事がこなくなるので注意してください。仕事を選ぶ必要があるのは「周りから優秀と認知されて、仕事がたくさん降ってくる人だけ」です。新人のうちは、仕事の内容にこだわらず、まずはたくさん引き受けてバシバシこなすことが、スタートダッシュに最も効果的です。
仕事を引き受けたら、最速で手をつけましょう。そして、進捗を自分から報告しましょう。
こうすることで、上司の負荷を減らすことができ、信頼されることができます。
僕がOJTリーダーをやったときにつくづく感じたのですが、任せた仕事をやっている素振りが見えなかったり、進捗連絡がなかったりすると、めちゃくちゃ不安になります。こうなると、自分の業務をやりながら、人の進捗を常に気にかけなければいけなくなります。これ、普通にパフォーマンスが下がるんです。正直「自分がやった方が早いから戻してもらおうかな」とさえ思っちゃいます。こう思われてしまうと、今後仕事を任せてもらえなくなる原因にもなりますし、信頼も得られません。
仕事の質を高めるには経験が必要ですが、スピードを高めることは誰にでもできるので、まずは速攻で手をつけ、1週間に1度は連絡・報告をしましょう。
ちなみに、よく「仕事は効果が高いものを選べ」とか言われますが、新人のうちからこれしてたら重要な仕事がこなくなるので注意してください。仕事を選ぶ必要があるのは「周りから優秀と認知されて、仕事がたくさん降ってくる人だけ」です。新人のうちは、仕事の内容にこだわらず、まずはたくさん引き受けてバシバシこなすことが、スタートダッシュに最も効果的です。
できる人の言動をメモりまくる
 これをやっている人ほぼいないと思いますが、僕は新人がスタートダッシュを切るのに必要な行動だと思っています。
理由は、上司の視点を学べるからです。
できる人の説明や発言を聞いていると、妙に納得感がありますよね。こう感じた時は、全てその発言内容と想定される意図や理由をメモることで、できる人が何を考えているかが大まかにわかります。ちなみに僕が新人のときにメモっていた例は、こんな感じでした。
これをやっている人ほぼいないと思いますが、僕は新人がスタートダッシュを切るのに必要な行動だと思っています。
理由は、上司の視点を学べるからです。
できる人の説明や発言を聞いていると、妙に納得感がありますよね。こう感じた時は、全てその発言内容と想定される意図や理由をメモることで、できる人が何を考えているかが大まかにわかります。ちなみに僕が新人のときにメモっていた例は、こんな感じでした。
(例1)
発言内容:Aを決める会議時、〜さんは進捗を遮ってまで「そもそもAというものの概念、それを構成するものと考え方」について、図を使って説明し出した。
想定意図:何かを決めるときは、まず構成要素を切り分けて、必要なモノ、不要なモノを明確にし、フォーカスを絞ろうとしている。「分ける」という考え方が大事そう。
(例2)
発言内容:Bという毎年行っている活動についての会議で、〜さんは「その活動の目的と必要人員、想定アウトプットはなにか」と聞いていた
想定意図:「活動の効果とリソースのバランス」を見て、活動の要否を判断している。毎年当たり前のように行われている活動でも、このバランスは常に見るようにしなければならない。
(例3)
発言内容:Cという問題が発生し、対応策はDかEの2択。自分はDが当然だと思っていたが、リーダーはEにした。
想定意図:発生した不具合件数は1件のみであったため、対策費用とかかる時間から考えると、Eの方が妥当であった。一見、恒久対策を取った方がいいように思えるが、バランスを考えて判断する必要がある。